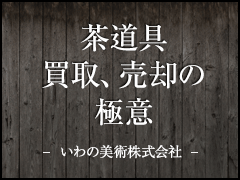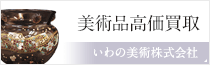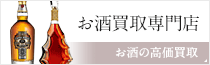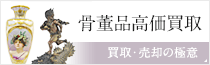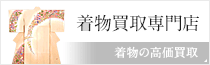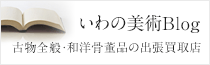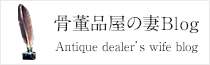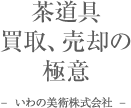懐石道具の基礎知識~懐石家具(漆器)
懐石道具の基礎知識~懐石家具(漆器)
懐石道具は茶事の折に出される食事の器の総称です。古くは漆器(懐石家具)が主流でしたが時代とともに料理も変化し、それに伴って陶磁器が取り入れられるようになりました。
ここでは懐石家具とも呼ばれる漆器について、茶道具資料をもとに説明します。
懐石家具(漆器)
 懐石では「一汁三菜を過ぐべからず」といわれます。この姿勢は日本伝統の本膳料理を源としながら、簡素を旨とする茶の湯が次第に作り上げたものとされています。
懐石では「一汁三菜を過ぐべからず」といわれます。この姿勢は日本伝統の本膳料理を源としながら、簡素を旨とする茶の湯が次第に作り上げたものとされています。
「一汁三葉」とは飯・汁・向付・煮物・やきものを基本とする軽い食事で、さらに茶事に欠かせない盃事が加わります。
この一汁三菜の器の中で飯椀、汁椀、煮物椀は漆器が主で、向付や、やきもの用の器には、陶磁器が多く使われます。また、盃事の際の酒器には、通常鉄製の燗鍋と漆塗の盃が用いられます。
懐石家具とよばれる漆器類は種類も多く、折敷、飯椀、汁椀、煮物椀、小吸物椀、飯器、湯桶、盆などがあります。
折敷・飯椀・汁椀
 折敷(おしき)とは膳のことです。折敷にのせられた飯椀、汁椀、向付が、懐石で最初に出される器です。
折敷(おしき)とは膳のことです。折敷にのせられた飯椀、汁椀、向付が、懐石で最初に出される器です。
折敷は四隅を切った角切、方形の角不切の2種を基本形とし、各種の塗物、木地に鉋目などの加工を施したもの、漆絵などで文様を施したもの、足をつけたものなど、方形だけでなく円形、半円形など様々です。
飯椀・汁椀も種類が多く、利休形だけで丸椀、一文字椀、上り子椀、面桶椀、吉野椀(黒塗りの地に朱漆で花卉文が描かれたもの)、精進椀などがあります。
利休形のほか、片桐石州、裏千家九代不見斎など各時代の茶人の好み物もあります。
煮物椀
 懐石の中心ともいえるのが煮物です。膳椀が出された後、しばらくすると煮物椀が出されます。
懐石の中心ともいえるのが煮物です。膳椀が出された後、しばらくすると煮物椀が出されます。
煮物椀に使われる椀も飯椀や汁椀に比べ、意匠豊かで、蒔絵などが施されたものがあります。
代表的なものとして、裏千家十一代玄々斎好の四季七宝蒔絵煮物椀があります。
このほか、江戸時代末期以降の塗師や蒔絵師によって、煮物椀が多くつくられています。また、現在では、桃山時代の秀衡椀や江戸時代初期の蒔絵椀などを見立てて煮物椀として使うこともあります。
小吸物椀
 料理が一通り済むと、小吸物椀に続いて、八寸が持ち出され、盃事が行われます。
料理が一通り済むと、小吸物椀に続いて、八寸が持ち出され、盃事が行われます。
小吸物は箸洗いともよばれるごく薄味のすまし汁です。椀もごく小振りの細長いものが多くみられます。
盃事が行われるようになったのは、江戸時代後期のことであるため、それ以前には小吸物椀はなく、裏千家の好み物で十代認得斎好の溜塗小吸物椀が古い例として知られています。
吸物は江戸時代前期から懐石に出されており、裏千家四代仙叟好の朱塗葎椀(筒形に近い姿の身に被せ蓋の付いた椀)、原叟好の葎吸物椀などが知られています。
酒器
 懐石では、酒器として燗鍋と盃が使われ、膳が出された後すぐに持ち出されます。
懐石では、酒器として燗鍋と盃が使われ、膳が出された後すぐに持ち出されます。
 かつては、漆器の酒次を使い、火にかけるときのみ燗鍋を使ったとされていますが、現在は特別な場合を除き、燗鍋をそのまま持ち出すことが多いようです。
かつては、漆器の酒次を使い、火にかけるときのみ燗鍋を使ったとされていますが、現在は特別な場合を除き、燗鍋をそのまま持ち出すことが多いようです。
酒次は溜塗の利休形を基本とし、燗鍋は姿、意匠が多様で素材も鉄、南鐐、銅、漆器など様々なものがあります。また、替蓋に漆器や陶磁器などの蓋をあわせて、その取り合わせを楽しむこともあります。
盃は朱塗のものが利休形として知られています。他にも玄々斎による好み物もみられますが、ほとんどが朱塗です。
飯器・湯桶・その他
 飯器は替えの飯を入れて回すためのもので、手付と手のないものとがあり、ともに杓子が添っています。
飯器は替えの飯を入れて回すためのもので、手付と手のないものとがあり、ともに杓子が添っています。
湯桶は懐石の最後に出される湯を入れるものです。胴に注ぎ口と手が付いています。湯の中には飯の焦げなどの湯の子が入れられているため、それをすくうための湯の子掬いという杓子が添っています。 その他、縁高という菓子を入れる器がありますが、これも懐石道具の中に含まれます。
 懐石道具は一揃えでつくることが多く、本来はその一式を懐石家具と呼んでいます。
懐石道具は一揃えでつくることが多く、本来はその一式を懐石家具と呼んでいます。
時代の流れとともに、懐石家具の内容も変化し、楪子(端反りの浅い木皿にやや高い足台をつけたもの)、豆子(小形な塗椀の飲食器)、引重(二段重ねの塗箱)など、現在ではあまり使われていない器が含まれている場合もみられます。
いわの美術では、懐石道具一式の買取を行なっております
状態によってはお取り扱いの難しい場合もございますが、骨董的価値のある古い時代の懐石家具(漆器)も積極的に買取しています。
まずは、お電話・オンラインフォーム・LINEにてお気軽にご相談ください。