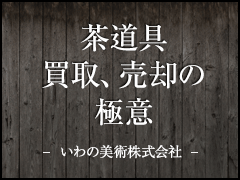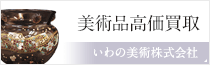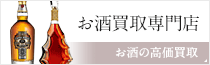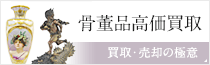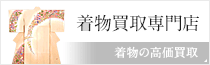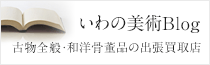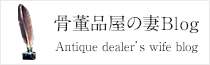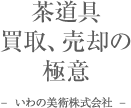花入とは
花入とは
 花入(はないれ)は、茶席に飾る茶花を入れる器です。
花入(はないれ)は、茶席に飾る茶花を入れる器です。
古くから花を身近に置いて自然の恩恵を生活の中に生かすことは、洋の東西を問わず行われてきましたが、日本で花を生けて荘るという習慣は仏教伝来と関わりがあります。
仏教が大陸から伝わるとともに、仏様にお花を供える「供花」の習慣も日本に入ってきました。これはいわゆる立花(華)と呼ばれるもので、それが華道の成立へとつながります。
 茶道において、花を生ける花器、花生けのことは「花入」といいます。他に花瓶、花立といった言い方もありますが、十六世紀に「分類草人本(茶道の成立期の茶法を伝える代表的な茶書の一つ)」に「花入」という用語が最初に用いられてからは、もっぱら茶道具として「花入」という呼称が使われています。
茶道において、花を生ける花器、花生けのことは「花入」といいます。他に花瓶、花立といった言い方もありますが、十六世紀に「分類草人本(茶道の成立期の茶法を伝える代表的な茶書の一つ)」に「花入」という用語が最初に用いられてからは、もっぱら茶道具として「花入」という呼称が使われています。
 花入の存在は、掛物と同様重要な存在とされています。
花入の存在は、掛物と同様重要な存在とされています。
中立のある正式な茶事では、初座の床の間に書画が掛けられるのに対し、後座では花入に生けた花が飾られます。これはすなわち、花と花入は、掛物に匹敵する大切な茶道具であるということを表しています。
また、中立を略した茶事の場合や大寄せの茶会などでは、床の間に掛物と花入をともに荘ることがありますが、これを「諸飾り(もろかざり)」といいます。
諸飾りでは、床の形状や掛物の種類によって花入を荘る位置や、花入をのせる薄板にも様々な規範があります。
花入の形状と種類
 花入は扱いによって、中釘や床柱の花釘に掛ける「掛花入」、床の天井や落掛などから吊る「釣花入」、床に置く「置花入」に分けられます。
花入は扱いによって、中釘や床柱の花釘に掛ける「掛花入」、床の天井や落掛などから吊る「釣花入」、床に置く「置花入」に分けられます。
花入の材質は実に広範囲で、工芸のほとんどの分類にわたります。金工、陶磁器、木、竹などが主ですが、口造りや耳、遊環の有無などにより、同じ材質でも形状や意匠が多彩です。
花入にも格があり、材質により下記のような「真」「行」「草」に分けられています。
 真の花入
真の花入
唐銅(古銅)、青磁、染付、彩磁、白磁、祥瑞、赤絵、交趾
畳床…真塗の矢筈板
行の花入
砂張、磁器の釣花入、瀬戸、丹波など釉薬のかかった国焼、唐銅の花入を写した楽焼
畳床…真塗、溜塗、掻合、春慶などの塗り物の蛤端の薄板
草の花入
南蛮、備前、伊賀など無釉の国焼、楽焼、竹、瓢、籠、木工など
畳床…木地の蛤端の薄板。ただし、籠花入には薄板は用いません。
※茶道の作法は、流儀によって異なりますが、ここでは裏千家の作法をもとに教本などに沿って紹介しています。