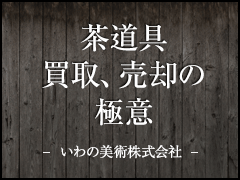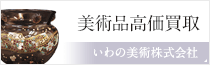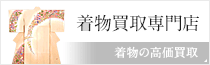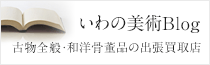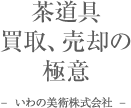井口海仙 茶杓 『待宵』

井口海仙
茶道家、号は宗含や幽静庵
経歴
明治33(1900)年、裏千家十三代圓能斎鉄中宗室の三男として京都に生まれました。
同志社を卒業後、大正11(1922)年、『茶道月報』を出版し、大正14年、兄の無限斎(淡々斎)が裏千家14代を継承すると、海外への茶道文化普及に積極的に取り組み、その補佐役として活躍しました。また裏千家今日庵の理事や淡交会専務理事、国際茶道文化協会理事などを歴任して大正・昭和の茶道会の発展に貢献しました。昭和57(1982)年81歳でその生涯を閉じましたが、随筆のほか、多くの編著書を遺し、茶道ジャーナリズムを牽引したことでも知られています。
活字で伝える茶の湯の世界
父の十三代圓能斎鉄中宗室(1893-1964年)は、現代茶道への道筋をつけた宗匠で、学校教育に茶道を取り入れたほか、茶道の作法を『小習事十六か条伝記』などの教本にまとめ、多くの茶人を養成したことで知られています。
昔の茶人が、茶の湯に関する自らの感懐を書きのこしているのはわずかで、千利休でさえ書簡に一、二言書き加えているのみで、弟子による著作のほかは、まとまったものはほぼないと言われています。当時、茶人のことばは、その弟子、または後世の人によって書き残されるもので、秘伝や口伝えを基本とする茶道の作法を書物にまとめることは極めて異例なことでした。しかし十三代の書物出版の功績により門戸が一般にも開放され、茶道は庶民の手に届く近しいものになりました。
海仙は、そのような父のもとで幼少期より茶の湯に親しみ、父に師事して作法のみならず、歴史や茶の美、茶人のこころ、名器や名物に至るまでを学んでいます。若い時より文才に長けていたという海仙は、父の教えにより受け継いだ茶道の精神を、家元に生まれた独自の目線で数多くの随筆に記していますが、それらには一般の社会生活にあてはめることが出来る言葉も多く見られ、茶を嗜む習慣がなくとも、とても興味深いものがあります。
茶杓
茶杓は抹茶を茶碗にすくい込むのに使う道具で、源流は中国にありますが中国では茶杓とは呼ばず、茶匙と呼び、材料も金・銀・象牙・べっ甲などで作られていたそうです。
日本でもその流れを汲み、象牙やべっ甲の茶杓が作られていましたが、独自の茶杓を作り、竹茶杓を日本の茶道文化における小道具に仕上げたのは利休でした。稀少で高価な材質を使ったものから、どこにでもある竹を用いて茶杓を作り、それを晴れの場において聖なる小道具に仕立てた利休は茶杓の革命者でもありました。侘び茶を大成させた利休よる『本来すべての人は平等であり日常の生活から断絶された特別な空間である茶室ではそれが可能になる』といった茶会の根本精神を具体化したものだとされています。
茶杓の観賞
茶杓は多くの茶道具のうち千家十職にもその専業の家はなく、古来、茶人自身が作ったものでした。下作りをする人が他にいた茶人もあれば、竹選びから仕上げまでの全てが自作の場合もありますが、最終の仕上げは例外なく茶人自身であったそうです。
したがって茶杓の観賞に重要なのは、作者がはっきりしていて、それが疑いもなくその作者の真作であることが証明されているという点です。
原則的に価値のあるものは、茶人や高僧、有名文化人などの作ったもので、茶杓が茶の湯で重要な位置を占めるようになるにつれ、作者が筒に〆印、銘、自分の名を署名したり花押を認めたりするようになりました。またその茶杓を贈る人に宛てた手紙や、同時代の作者と親しい人物が「この茶杓は確かにこの人の作である」という証明書の役目をした添え状を書いたり、筒書を書き添えたり、なかには、筒がなく、直接箱に収め、箱に銘と自署を書いたものもあります。
代表的な作者と作品
茶杓には茶人の魂がこもっていると言われるほど作者その人の人格が表れていて、海仙の他にも多くの茶人がそれぞれ個性的な作風で名作を残しており、興味深いものがあります。
珠光時代の珠徳や羽淵宗印は、薄作りで美しい茶杓を削りました。伝珠光作の「笹葉」や「茶瓢」、紹鷗(じょうおう)の「浅芽」は、利休以前の過渡期の作品として貴重です。言わずと知れた利休は、中節でアリ腰の形をつくって茶杓を完全に日本化しました。多くの代表作の中でも「虫喰い」や「泪」は傑作として知られています。
また古田織部は、利休の形を一層自由で新鮮なものに発展させ、数々の名杓を残しています。
小堀遠州の「有馬山」や「窓竹」、片桐石州の「稲羽州(いなうしゅう)サマ」などは、当時の武家茶道のリーダーとしての風格さえ感じる作品といえます。他にも宗旦による作品は漆ぶきしていないのが特徴で「松風」にみるような全体に胡麻の散った侘びた風情がみごとです。